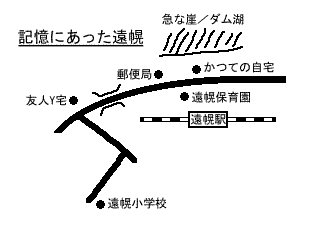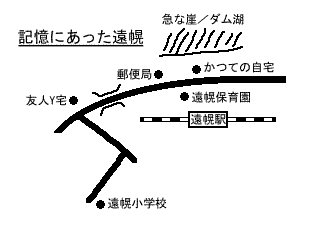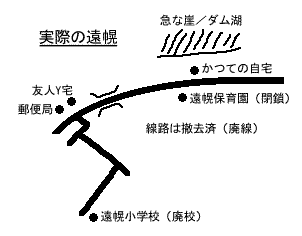『ハロー・エンホロ』
私は三歳から七歳までの間、北海道の遠幌という名の小さな町で暮らしていた。その街は、南大夕張炭鉱で採掘された石炭を都会へ輸送するための輸送路に位置し、炭鉱労働者が多く住んでいた。
父親の転勤で遠幌を去ってから二十余年、テレビでも大きく報道された炭鉱事故と、それにともなう鉱山の閉鎖から二十年が経過した今、私は友人の結婚式出席を機に、遠幌を訪問するチャンスを得た。
これは記憶をたどりながら書いた、遠幌の略図である。
自宅のとなりには駄菓子屋があり、よく入りびたっていた。友人Y宅には頻繁に遊びに行き、彼の部屋でピンクレディーのレコードを聞いた記憶がくっきりと残っている。他にも仲の良い友人はいたが、その家の位置までは思い出せなかった。
さて、まず駅のあった場所に到着して、驚いた。駅も線路も存在しないのだ。車で移動していたため、あやうく見逃して通り過ぎてしまうところだった。駅の通り寄りにある保育園が、かろうじて「その場所」を教えてくれていた。が、その保育園も、窓に板がうちつけられており、父親とキャッチボールをしたり、自転車に乗る練習をしたりした広場も、雑草に覆われて荒れ放題になっていた。
かつての自宅があった位置を見ると、そこには見知らぬ真新しい家が建っている。家の裏手にある崖とダム湖は記憶の通りだが、家の脇の家庭菜園は、記憶にあるものよりも小さく見えた。
となりの駄菓子屋を探したが、古い長屋(炭住)があるばかりで、店舗らしいものはどこにもない。犬に吠えられたので退散し、一年間だけ通った小学校へ向かうことにした。
学校へ向かう途中の道には、郵便局と橋、友人Y宅があったと記憶している。郵便局の位置以外は、おおむね記憶の通りだった。が、肉屋をやっていたはずの友人Y宅は、シャッターがおりていて、人のいる気配がない。閉山から長い時間が経過し、Yもまたよそへ越していったのだろうか。
学校の手前の道は急な上り坂で、積雪のあった朝などには、児童たちが教師の車を押してあがっていた。その坂道は記憶の通り存在していたが、両脇から大きくせりだした草木が、景観を一変させていた。道が植物に食われている、そんな印象がある。
その坂をのぼりきったところに、小学校は確かに存在していた。が、その荒れ具合からして、長期間放置されていることは明らかだった。私の身長ほどもある雑草が、まるで密林のように繁っている。雑草の向こうに見える校舎へ近寄ろうにも、どこから近寄ればよいのか判らない状態であった。
近寄りがたい雑草の林の向こうに、傷んだ木造の校舎がただ粛然とたたずんでいた。
学校の敷地に入ってすぐの位置には、「閉校記念碑」なるものが建っていた。建てられたのは、平成二年とある。約十年、この学校は放置されていたのだろうか。いや、そうでもないらしい。まだ新しいわだちが、グラウンドがあったと記憶している方向へ伸びている。閉校になってからも、誰かが車で乗り入れているようだ。
わだちはグラウンドへ向かい、グラウンドに丸い円を描いていた。それ以外の場所は、やはり丈の高い雑草に覆われてしまっている。グラウンドに面した体育館の出入り口が破壊されており、そこから校舎の中に入れそうだった。
薄暗い建物の中に入ると、記憶が津波のように押し寄せてくるのが感じられた。
小さな体育館、その壁にかけられた各年度の卒業製作の絵、床にひかれた緑色のライン、狭いステージ、体育用具室。そのすべてが、記憶を刺激するのだ。が、体育館の天井の一部は抜け落ち、その部分から入り込んだ雨で床は腐っていた。体育用具室の板をうちつけられた窓からは、木の枝が入り込んできている。
体育館から渡り廊下を通って校舎へ。
一般教室に残されたカレンダーは、平成二年二月で終わっていた。音楽室に残されていたオルガンは、痛んでいたものの音はしっかりと鳴った。放置されていたダルマストーブは、今でも使えるのだろうか…。残されたロッカーは、消火器は、机、椅子、黒板、チョーク………。
建物の死。
町の死。
すべては過去のもので、存在しない。人間の営みの、なんと小さいことか。時がたてば、何ひとつ残らない。あと十年もすれば、校舎もまた、植物に食われて消えていくことだろう。閉校記念碑でさえ、草木に埋もれて誰にもかえりみられなくなるに違いない。
私は記念碑に刻まれた校歌の歌詞を見ながら、心の中で歌った。たった一年間しかいなかった小学校の校歌であるにもかかわらず、その旋律は記憶に刻み込まれている。
光に映える丘の上
夕張岳の気高さを
磨き鍛えた身と心
希望わきたつ学舎は
われらが遠幌小学校
心の中で歌い、そのセンチメンタルな行為を自嘲しながら、私は学校を後にした。
引き上げる途中、Y宅に車が停まっているのを見た。誰かいるのだ。
私はおそるおそる声をかけてみる。
「ごめんください」
三度ほど声を出すと、家の中から年配の女性が姿をあらわした。ひとめ見て、私は彼女がYの母親であることがわかった。彼女も、私が名乗ると即座に思い出してくれた。
「あなたも変わらないねぇ」
Yの母は懐かしそうにそう言う。
「友人の結婚式で、近くまで来たものですから」
「あら残念。うちのヒデは今、キャンプに行ってるのよ。あなたとも同級生だったS君やW君と一緒に」
そう言われて初めて、私はYの名を記憶していなかったことに気付いた。「ヒデ」がつく名前だったろうか。思い出せない。それに同級生のSとW? わからない。彼らの顔は? なにもわからない。仮にYに会えたとして、その顔を見て思い出せるのだろうか?
私はしばらくYの母と会話して、そのまま立ち去った。連絡先を聞くでもなく、連絡先を残すでもなく、ただ立ち去った。
そもそも、何を話すことがあるのだろうか。
携帯電話が圏外になる町。すでに死んだ町。そして、その町にしがみついている人々。かろうじて生きのびている近隣の町へ出て、働いている人々…。
間違いない、私はアウトサイダーになってしまっているのだ。町も人も、もはや私にとってリアルなものではなくなってしまっている。
二十年という歳月。
それは永遠にも等しい。
滝澤(1999/08/01)
このページの作品に対するご意見・ご感想などは、E-Mail : maniactaki@gmail.comまでお願いいたします。
※スパム対策のために「@」を全角にして掲載しています。半角に直してお送りください。